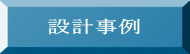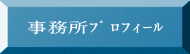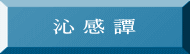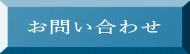~ 第21節 コーヒーブレイク・6
… 私の冬景色 ~
今年の冬は例年になく寒い。
つとに寒がりの私だからそう感じるのかと思ったが、世の中、湯タンポが
飛ぶように売れているそうだ。
" 湯タンポ "...なんと暖かそうな響きだろう。
あの頃...、隙間だらけの我が農家住宅は、冬の陽が落ちればどの部屋にも
シンとした冷たい空気が満ち溢れていた。
そんな中、『 おやすみぃ~ 』と、白い息を吐いて、重い綿ぶとんを持ち上げ、
足元の湯タンポを確かめられた時の、何とも言えぬ有り難さは忘れられない。
しかし...。
あの頃...、私は必ず湯タンポを足でたぐり寄せ、抱いたまま横になり、
ついぞ眼を閉じる事が出来ないでいた。
そしてそっと布団から起きだし、台所の明かりを頼りに、そこに立つ
母の背に私はすがるように聞いた。
『 かあちゃん...、なんで人間は死ななくっちゃいけねぇんだ... 』
振り返った母は戸惑いを隠せず、一瞬間をおいて、
「 まだ寝てねぇんか...、なんでそんな事聞くんだ...、5年生はそんな事
考えなくっていいんだ...、早く寝ろ... 」
そう言うが早いか、くるりと再び私に背を向けた。
やみくもの問いが、何故人の死なのか...。
何故それが小学校5年生の息子の問いなのか...。
母は背中を見せる事で、息子にその愚問さを伝えたかったのだろうが、
しかし、まかないをするその手は止まったままだった。
私は、また白く長い息をひとつ吐いて、寝床に戻るしかなかった。
そしてまた湯タンポをかかえたのだが、眠るどころか寝返りを繰り返し、
とうとう死の怖さに奇声をうなり、真っ暗な闇の中で枕を濡らすばかりだった。
あの頃...、私はどうしてか格段にませた小学生だった。
小学校の入学式には、頭ひとつ抜けて、身体もガッチリと大きく、
担任の先生は、〝 伸ちゃんは本当に可愛くなかった〝 と、今でも口にされる。
以来、身長差はそのまま続き、ガキ大将を続けた。
学校では何事も仕切っていた。
勉強は良く出来なかったけれど、不思議と成績は悪くはなかった。
先生の前では、やたら良い子を演じる自信があって、学級委員長としての
権力を知り、スポーツ選手としての華も味わっていた。
あの頃...、私は野球に明け暮れた。
現代の硬式クラブは勿論、スポーツ少年団すら生まれるずっと前だ。
野球部もない田舎の小学校で、放課後に同級生の仲間を集めては、
校庭にすり足でラインを引いた。
そんなインスタント球場の跡が、地表から消える事はなかった。
ボールを追って夕方になると、仲間全員の帰路ルートを頭の中に作り、
一人ひとりそれぞれの家まで一緒に送った。
最後の一人を送り届けても、私は家に帰らず、今度は隣にある中学校の
野球部の球拾いを、まるで猟犬の様に続けていた。
ファウルボールを探しては選手に届け、ブルペン捕手の後ろで
投球数を一緒にかぞえた。
中学生との会話は、自分の人生への期待を無限にさせた。
ピッチャーで4番の私は、自分のグローブ以外のミットもバットもボールも
ベースも、全て自前でそろえた。
無理やり一つ上の6年生に即席のチームを作らせ、やっつけては悦に入っていた。
それがエスカレートして、隣町の小学校の野球部と対外試合をした事が発覚し、
首謀者の私は校長室に、おすわりをさせられた。
しかし反省どころか、そこで野球部の発足を懇願し、おすわりの時間を長くした。
休日にはみんなを引き連れ、高校野球の大会を見に、電車に乗って宇都宮に
出かけた。
一人で見に行く時には、わざと応援団の女子高生の中に陣取って、可愛がられる
すべを駆使した。
その頃、すでにいくつかの有力高校の校歌を暗唱し、スタンドから絶唱していた。
家で一人になった時は、我が家にあった石倉の壁をキャッチャーに見立て、
16m離れた手製のマウンドから、野球を実況するラジオアナウンサー役も
こなしながら、ひたすら投げ続けた。
およそ200球を一日のノルマにした私の肩の強さは、中学生にもひけをとらなかった。
将来ピッチャーとして甲子園を沸かせ、プロ野球で生きる事は、
なんら夢というよりも、当たり前に想像していた事だった。
そしてあの頃...、なんとも同級生の女の子たちが好きで仕方がなかった。
父の圧力に屈して書いていた当時の日記帳には、日替わりで好きな女の子の
名前が出てくる。
毎日、好きな女の子に会いに行く為の学校ですらあった。
学級委員長は、翌朝の問題を教室の黒板に書いてから帰る事が日課であり、
一人黒板に向かう私を、私の好きなませた女の子たちは、校庭から窓越しに
見ていてくれた。
〝 ねぇ...伸ちゃん...、誰が好きなのぉ...? 〟
そう問われた私は、事もあろうにそこにいた女の子たちの名前を、
全部黒板に書いた。
あの時代のませたガキどもの、甘い時間と空間がそこにあった。
あの頃...、小学校5年生の私は、男として輝いていた...。
事実そう感じていた...。
人間の一生には、最も輝く時が誰にでも一度はあるそうだ。
私にもいずれその様な時が訪れてくれたら良いのだが、残念な事に私はすでに
あの頃...、人生の絶頂を迎えていたに違いない。
そしてあの頃...、父が倒れた。
ただ怖いだけの男が、病院のベットで泣き伏していた。
それは、わたしの知る父ではなく、その異様な光景に私は震えた。
半身不随となった父の病を知るに及んで、私は母の事、家の事を考えた。
しかし何も浮かばなかった。
母は早朝から深夜まで会社員となり、私に出来る事は放課後早く家に帰り、
父の下の世話をする事だけだった。
小学校5年生の無力を知らされ、しばらくの間、みじめで悔しくて
授業中も泣いていた。
そんな私を、野球の仲間も、女の子たちも見ないふりをしてくれた。
人間の一生には、絶望の淵をさまよう事が、誰にでも一度はあるそうだ。
私にもいずれその時が来るのだろうが、出来る事ならあの頃...、
すでに人生の絶望を歩いていたとなれば有り難いと思う。
あの頃に味わった絶頂と絶望。
共にその時こそ、人間は必然の死を恐れるらしい。
5年生の私は、それを30歳を超えたばかりのうら若き母の背に問い、そして
泣きぬれたのだった。
父もそれから7年後に回復なきまま他界し、以来、人には
〝 伸ちゃんは苦労したね... 〟と、よく言われる。
しかし、死を恐れず、生に立ち向かって子供たちを育てて来た母の姿を
見ていただけで、私は何の苦労もしなかった。
私もいまさら、人の死を何故だとは問わなくなった。
でも、今もし、同じように母に問うたら何と言われるだろう。
やはり「 早く寝ろ 」と言われること請け合いだが、かといって寝室の随分薄くなった
良質の羽毛のかけ布団を引き上げたところで、あの湯タンポはもうない。
抱いて身も心も温まった湯タンポが消えたのは、いつの冬からだろうか...。
今でこそ電気毛布に身をくるむ私だが、冬の布団に入る時、私は台所の明かりを目指し、
絶頂と絶望を母にぶつけた5年生の自分を想いだす。